認識力関係で検索し、このページにたどり着いた方へ
現在、記事を色々調整中で、認識力に特化した話は別記事に切り出しました。
別記事で、認識力概要と鍛え方を解説したので、そちらをご覧ください。
弐寺をプレイしている人なら誰でも、「上手くなりたい」と思っていることでしょう。
そのための近道は、弐寺の実力を構成する、小さな実力それぞれをしっかり伸ばすことです。
…とはいっても、そんなのいきなり言われても分からないと思います。
そこで、この記事では、弐寺における「実力」を大きく3つに分け、それぞれの概要を説明します。
次に、それらを可能な限り分解し、その全体像を確認できるようまとめていきましょう。
そして、このまとめを使ってどのように練習していけばいいかも解説していきます。
3つへの分類は初心者向け、細分した全体像は中級者以上向けを想定しています。
私は、今こそ弐寺をやっていないものの、過去に皆伝を取得した経験があります。
その時にもこういった内容を考えていたので、それをお伝えしていきましょう。

ただ闇雲にプレイしていても、効率は悪くなるよ!
弐寺の実力3分類
弐寺の実力は、大きく分けると以下の3つで構成されています。
- 認識力
- 処理力
- 操作力
処理力と操作力は私が勝手に作った言葉です、多分他では通じないので気をつけてください。
この分類をわかりやすくするため、弐寺をプレイするときの流れを出しましょう。
ここでのプレイは、実際に譜面をプレイしている時を指します。
まず、降ってきたノーツを目で見て、どうなっているか認識します。
次に、指をどう動かせばいいか、皿ならどのように回せばいいか処理します。
そして、処理した通りに指を動かし、ボタンや皿を操作します。
この3ステップそれぞれで必要な力が、「認識力」、「処理力」、「操作力」です。
順に、詳細を見ていきましょう。
認識力
まず認識力、譜面を見て、どうなっているかを把握する能力です。
言い換えれば、インプットする能力、でしょうか。
当然、基本的には譜面の密度が高くなると必要な認識力も上がってきます。
例外はありますが、ここで出すとややこしくなるので控えておきます。
認識力が足りないと、譜面がまるで模様でも降ってきているかのように見えるでしょう。
あるいは、指がピタッと動かなくなるかもしれません。
このように、あるラインを越えると明確なサインが出やすいのも特長です。
ここで認識をした後、処理や操作が待っているのですが、そもそもの認識ができないとその先も何もできません。
だから、この不足は比較的分かりやすいのです。
上級者になるとよく耳にすることになりますが、認識力は「縦認識」と「横認識」に分けられます。
それについては別記事で解説したので、気になる方は是非そちらをご覧ください。
処理力
次に処理力、認識した譜面をどう叩くか判断する能力です…が。
実はこれ、弐寺においてはそこまで難しくありません。
どの鍵盤が降ってきたらどの指を動かすか、と言い換えると分かるかもしれませんね。
そう、「運指力」が、弐寺における処理力になります。
だから、弐寺において処理力の練習は「しっかり運指を練習しましょう」と言い換えられます。
この運指については、すでに別記事で解説しています。
まだ運指を固定してないという場合は、そちらも参考にしてみてください。
ちなみにですが、私は皆伝に至るまで、運指に関してこれ以上の特別なことはしていません。
実際、ここはほぼ自動的に行われるようになる部分です。
最初の運指使い始め以外では、そこまで意識しなくてもいいでしょう。
操作力
そして操作力、実際に指を動かす能力で、一般には「地力」と呼ばれるものの1つがこれです。
「地力」という言葉は、この操作力、あるいは弐寺の実力全体を指すことが多いです。
認識力のインプットに対して、こちらはアウトプットする能力と言えるでしょう。
この操作力、後の細分化を見てもらえれば、詰まっている要素の多さが分かると思います。
そのどれが今不足していて、伸ばすべきポイントかを把握することが、上達への近道です。
もちろん、各楽曲は細分化した能力の1つだけで構成されてるわけではありません。
満遍なく色々な能力を伸ばすことで、初めて上達できることもしっかり認識しておきましょう。
なお、これが不足している場合にどうなるかは、いくつかあります。
- ミスがポロポロ出始める
- 体力譜面でもないのに、異様に体力を消費する
- 精度が悪くなる
- などなど
譜面がどうなってるかは分かる(=認識はできている)けど、叩けないパターンがこちらの不足のサインでしょう。
実力全体像
上で3つに大きく分けましたが、実際に上達を考えて伸ばす時には、この分類では足りません。
可能な限り細分化し、それ以上分けれない1つ1つを、着実に伸ばす必要があります。
そこで、私なりに弐寺の実力をできるだけ細分化してみました。
あくまで1つの形ですが、是非参考にしてみてください。
- 認識力
- 譜面認識力
- 縦認識
- 横認識
- 皿認識
- 枚数
- 押し引き
- タイミング認識力
- 目押し
- リズム押し
- 譜面認識力
- 処理力
- 操作力
- 鍵盤力
- 階段
- 単発階段
- 階段(狭義)
- 同色階段
- 二重階段
- 同色二重階段
- 移植二重階段
- 螺旋押し
- 坂
- 単発階段
- 同時押し
- 同時押し
- 隣接同時押し
- 鍵盤数の多い同時押し
- 全押し
- 縦連
- 微縦連
- 縦連
- 縦連複合
- トリル、デニム
- トリル
- 単発両手交互トリル
- 単発片手トリル
- 複重トリル
- ゴミ付きトリル
- デニム
- トリル
- 軸押し
- チャージノート、BSS
- CN+鍵盤
- CN脳トレ
- 乱打
- 単発乱打
- 複重乱打
- 階段
- 皿力
- 連皿力
- 偶数皿
- 複合力
- 左手・皿+鍵盤力
- 右手・片手力
- 鍵盤力
これは、記事を書きながらある程度考えて浮かんできたものを書いています。
恐らく、足りていません。
私も見直しながら、さらに細分化できるところはしていきます。
逆に、分けすぎているものも合体させたりと、ブラッシュアップしていくことにしましょう。
ちなみに、一部あえてここには入れていないものもあります。
例えば、「発狂」、「ソフラン」などですね。
発狂は属性に関わらず局所的に難化した譜面を指していて、特定の要素には分類できないから外しました。
ソフラン(速度変化)も1つは同じく特定の要素には分類できないという理由、もう1つは曲単位の攻略が必要になる場合がある点で外しています。
ようは、他の能力がその練習になる、あるいはそれを練習しても他に活かしづらい要素です。
…とはいえ、ソフランは低速力という、別の能力があるのも事実。
これも、どこかで記事にするかもしれません。
細分化した実力リストの使い方
では、最後に上のリストをどう使うかを説明しましょう。
以下の流れで進めていきます。
- どの項目を鍛えるか決める
- どうやって伸ばすか考える、あるいは調べる
- 鍛える前の状態を確認する
- 鍛える
- 成果を確認する
順に、詳細を見ていきましょう。
どの項目を鍛えるか決める
まず、自分が苦手だと思う実力を、上の中から1つ選択してください。
当然、ここで選択したものをこれから鍛えていきます。
これまでのプレイした感覚で「苦手だなぁ」と思うものでもいいですし、ミスカウントが多い曲の譜面傾向を選ぶでも大丈夫です。
操作力ならミスカウントで見ればいいですが、認識力は感覚なのでちょっと分かりづらいです。
上で出したように、見えなくなるラインを超えているかどうかで判断するといいでしょう。
どうやって伸ばすか考える、あるいは調べる
鍛えたいものを選んだら、それをどうやって伸ばせばいいかを考えます。
あるいは、調べて納得のいくものを選択する、でも構いません。
当ブログでも、(全てを解説するかは分かりませんが…)共通した考え方はまた別途記事にします。
それも、是非参考にしてみてください。
鍛える前の状態を確認する
練習方法も決まったら、早速練習…ではなく、まずは今の状態を確認しましょう。
練習の成果を確認するための、まずは元の状態のチェックですね。
できればミスカウントなら写真を撮るなり、感覚ならどうだったかをメモに残すなりすると後で比較しやすいです。
鍛える
事前チェックも済めば、あとはひたすら先ほど考えたメニューで練習あるのみ。
内容やレベルにもよりますが、大体1週間か2週間程度したら、次のステップに進みましょう。
成果を確認する
最後、もう一度最初チェックした時と同じ譜面で状態をチェックします。
その結果、改善されていれば練習の成果があったことになります。
もちろん、何も変化がない場合や、悪化していることもあり得ます。
その原因は、練習期間が足りないか、練習方法が間違っているかのことが多いので、そこを見直しましょう。
以降はこの繰り返しです。
また新しい内容に取り組むでもいいですし、さらに同じ内容を伸ばすでもいいでしょう。
認識力、操作力それぞれの具体的な練習方法
ここから、もちろん例外はありますが…多くの場合に使える練習方法を提示しましょう。
とはいえ、認識力と操作力でやり方が異なります。
それぞれ見ていきましょう。
認識力は、見えるギリギリを練習する
まず認識力、こちらは見えるギリギリのレベル帯を周回するのがオススメです。
イメージとしては、その密度の譜面に目を慣らし、それよりちょっと上まで見えるようにする感じでしょうか。
それを少しずつ繰り返し、上限を伸ばしていくのが基本方針になります。
操作力は、1段階下のミスを減らす
それに対し操作力、思い切ってプレイのレベル帯を1段階落としましょう。
例えば、現在☆10挑戦相当なら、☆9に。
そのレベル帯の、ミスカウントを減らす練習が効果的です。
操作力はスポーツをイメージしてもらうと分かりやすいでしょう。
スポーツは基礎となる体力をつけて、その次の段階に進むことが多いです。
弐寺でも、一段階下が基礎となり、それをより確実にこなすことで次に進みやすくなるのです。
また、ミスカウントとも相談ですが、常時ハードゲージでやるのもかなりオススメです。
ハードゲージだと一個のミスが命取りになりかねません。
常にミスを減らす意識がはたらくことにより、丁寧に取る良いクセがつきます。
これがかなり効いてくるので、是非やってみてください。
まとめ
今回は、弐寺の実力を深掘りしてみました。
細分化した表は上を見てもらうとして、大雑把な分け方は以下の通りでした。
- 認識力:譜面を見て、どうなっているか把握する能力
- 処理力:認識した譜面をどう叩くか判断する能力
- 操作力:処理した内容で、実際に指を動かす能力
処理力、操作力は当ブログでしか使えないことにも注意です。
そして、細かい実力の伸ばし方は以下の通り。
- どの項目を鍛えるか決める
- どうやって伸ばすか考える、あるいは調べる
- 鍛える前の状態を確認する
- 鍛える
- 成果を確認する
これらを常日頃から意識し続けることは難しいと思います。
私自身、現役時代常にこれらをやっていたかと言われると、正直NOです。
しかし、意識してやっていた時期は、やっていなかった時期に比べてしっかり伸びた感触もありました。
実力は、一朝一夕ですぐに伸びるものではありません。
焦る気持ちは分かりますが、落ち着いて一個一個丁寧に伸ばしていきましょう!
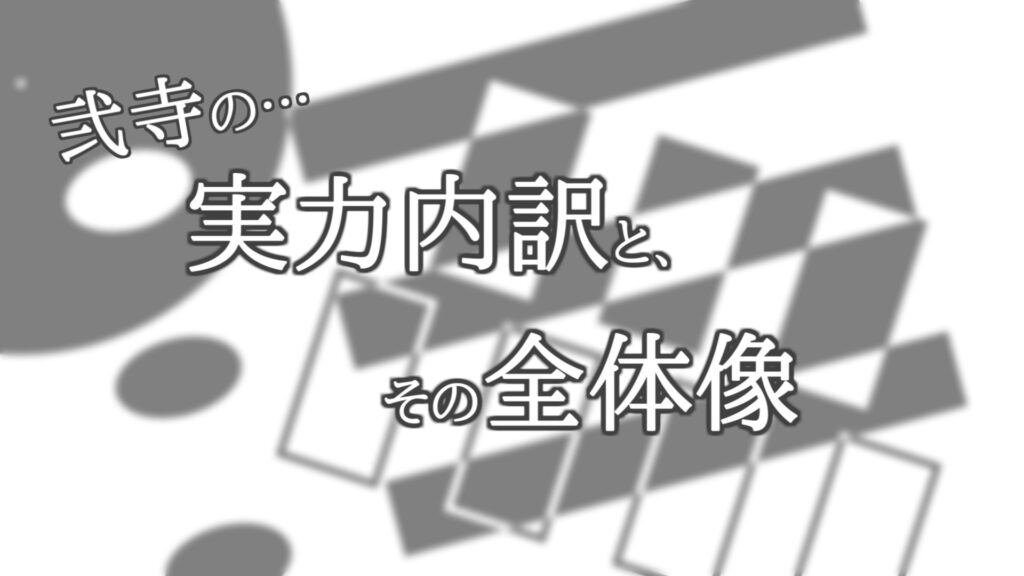
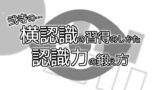



コメント