前回は、フェルマーの最終定理の紹介と、
どこをどうやって証明するか、
それに使う無限降下法というものを解説した。
前回の記事はこちら↓
フェルマーの最終定理を一部証明してみよう-あらすじ編- | Shino’s Mind Archive
今回はいったん別のお話になるので、
いきなりこちらをご覧いただいている方も安心して欲しい。
今回は、とある式変形を行う。
何かというと、三平方の定理に関するものだ。
補題として提示し、
それを証明するところまでやってしまおう。
念のため、補題とは証明に使う補助的な定理だ。
それ自体も証明が必要だが、
証明できれば別の証明の中で使うことができる。
補題:三平方の定理の式変換
先に書いておくが、この補題名は私が適当につけただけのものだ。
以下の補題を証明していく。
互いに素な自然数\(x, y, z\)について、
三平方の定理の関係が成り立っているとする。
$$x^2 + y^2 = z^2$$
このとき、二つの互いに素な数\(p, q\)を用いて、
以下のように表すことができる。
$$
\begin{equation}
\left \{
\begin{array}{l}
x = p^2 – q^2 \\
y = 2pq \\
z = p^2 + q^2
\end{array}
\right.
\end{equation}
$$
なんだこの形って感じだと思うが、
大丈夫、これから証明していく。
が、その前に一つ言葉を説明しておこう。
互いに素という用語が出てきている。
これは、最大公約数が1であることを表している。
つまり、\(x, y, z\)の最大公約数は1だし、
\(p, q\)の最大公約数も1である。
証明
では、早速証明を始めよう。
\(x, y\)の奇偶について
まずは、\(x, y\)の奇偶を調べよう。
ともに偶数か?
まずはこのパターン。
\(x, y\)ともに偶数かどうかを調べよう。
両方とも偶数と仮定して、\(x = 2a\)、\(y = 2b\)と置く。
で、三平方の式に代入してみよう。
$$(2a)^2 + (2b)^2 = z^2$$
$$4a^2 + 4b^2 = z^2$$
$$4(a^2 + b^2) = z^2$$
さて、これで左辺が偶数だと分かった。
つまり、\(z^2\)も偶数だ。
ということは、元の\(z\)も偶数となる。
というわけで、\(x, y, z\)全て偶数…2の倍数となった。
ところが、前提を見てみると、
これらは互いに素だと言っている。
つまり矛盾、\(x, y\)が両方とも偶数という線は無くなった。
ともに奇数か?
次にこちらを見てみよう。
いったん両方奇数として、
\(x = 2a – 1\)、\(y = 2b – 1\)と置いておく。
そうしたら、上と同じように
三平方の定理へ代入してゴリゴリ変換していこう。
$$(2a – 1)^2 + (2b – 1)^2 = z^2$$
$$4a^2 – 4a + 1 + 4b^2 – 4b + 1 = z^2$$
$$4(a^2 – a + b^2 – b) + 2 = z^2$$
先ほどと同じように、
左辺が偶数なので\(z^2\)も偶数、元の\(z\)も偶数だ。
ここで、\(z = 2c\)と置いてさらに計算してみよう。
$$4(a^2 – a + b^2 – b) + 2 = (2c)^2$$
$$4(a^2 – a + b^2 – b) + 2 = 4c^2$$
$$2(a^2 – a + b^2 – b) + 1 = 2c^2$$
左辺が奇数、右辺が偶数、明らかにおかしい。
というわけで矛盾が発生してしまったので、
この線も無くなった。
つまり、\(x\)と\(y\)は奇数、偶数の組み合わせだと分かった。
なお、片方を奇数、もう片方を偶数と決めてしまっても、
反対の場合は文字を入れ替えれば同じ議論で進められる。
そのため、ここでは\(x\)を奇数、\(y\)を偶数と
固定してしまおう。
ちなみに、\(z\)の奇偶は?
結論から言ってしまうと、奇数だ。
まず、\(x = 2a – 1\)、\(y = 2b\)と置いて、また計算する。
$$(2a – 1)^2 + (2b)^2 = z^2$$
$$4(a^2 – a + b^2) + 1 = z^2$$
ちょっと省略したが、こうなった。
左辺は奇数なので、\(z^2\)は奇数、
元の\(z\)も奇数ということになる。
式を変形していこう
では、元の式をちょっといじろう。
\(x\)を移項し、因数分解する。
$$x^2 + y^2 = z^2$$
$$y^2 = z^2 – x^2$$
$$y^2 = (z + x)(z – x) \tag{1}$$
このとき、\(z + x\)と\(z – x\)はともに偶数である。
\(x, z\)が両方とも奇数だからだ。
つまり、別の文字\(J, K\)を使って、
以下のように書き直せる。
$$
\begin{equation}
\left \{
\begin{array}{l}
z + x = 2J \\
z – x = 2K
\end{array}
\tag{2}
\right.
\end{equation}
$$
\(J\)と\(K\)の関係
では、ここで\(J\)と\(K\)が互いに素であることを示す。
これも背理法で攻めよう。
まず、\(J\)と\(K\)には2以上の最大公約数が存在すると仮定し、
それを\(g\)と置く。
これを使って、\(J\)と\(K\)を以下のように書き換えておく。
$$
\begin{equation}
\left \{
\begin{array}{l}
J = gj \\
K = gk
\end{array}
\right.
\end{equation}
$$
これを、(2)式に代入する。
$$
\begin{equation}
\left \{
\begin{array}{l}
z + x = 2gj \\
z – x = 2gk
\end{array}
\tag{3}
\right.
\end{equation}
$$
この二つの式を使って、少し変形する。
まず、\(z\)を表す形へ、(3)式のそれぞれの辺を足そう。
$$2z = 2gj + 2gk = 2g(j + k)$$
$$z = g(j + k)$$
これで、\(z\)が\(g\)の倍数だと分かった。
次に、\(x\)を表す形へ、(3)式の上から下を引く。
$$2x = 2gj – 2gk = 2g(j – k)$$
$$x = g(j – k)$$
\(x\)も\(g\)の倍数のようだ。
では、これらを(1)式の一個前…
\(y^2 = z^2 – x^2\)に代入しよう。
$$y^2 = (g(j + k))^2 – (g(j – k))^2$$
$$y^2 = g^2(j + k)^2 – g^2(j – k)^2$$
$$y^2 = g^2((j + k)^2 – (j – k)^2)$$
ここで止める。
さて、右辺は\(g^2\)の倍数なので、
左辺の\(y^2\)も\(g^2\)の倍数。
つまり、元の\(y\)は\(g\)の倍数となる。
よって、\(x, y, z\)全て、\(g\)の倍数となる。
…何か、おかしいことにお気づきだろうか。
実は、そもそもの前提で、
\(x, y, z\)は互いに素だと言っていた。
矛盾だ。
というわけで、\(J\)と\(K\)が互いに素であることが示せた。
式変形続き
では、ちょっと戻って式変形を続けよう。
(1)式…\(y^2 = (z + x)(z – x)\)に、
(2)式…\(J\)と\(K\)を使ったものを代入しておく。
$$y^2 = 2J \times 2K$$
$$y^2 = 4JK \tag{4}$$
ここで、\(J\)と\(K\)は互いに素なので、
両方とも平方数となる。
ここもちょっと補足しておこう。
まず、平方数を素因数分解すると、
各素因数の指数は必ず偶数となっている。
右辺について、4は\(2^2\)なので、素因数2の指数は偶数だ。
つまり、\(JK\)の各素因数も指数は必ず偶数になる。
さらに、\(J\)と\(K\)は互いに素…これを言い換えると、
共通の素因数を持たないということになる。
ということは、\(y^2\)の各素因数は、
丸ごと\(J\)、\(K\)のいずれかに含まれることになる。
例えば、\(y^2\)の素因数に\(3^2\)が入っていたら、
これは\(J\)、\(K\)いずれかに含まれ、
もう片方には素因数3自体が存在しない。
そうすると、\(J\)、\(K\)の各素因数の指数も、
必ず偶数となるのだ。
よって、\(J\)、\(K\)はともに平方数となる。
話を戻そう。
今、\(J\)と\(K\)がともに平方数だと分かったので、
更に別の文字で置き換えよう。
\(J = p^2\)、\(K = q^2\)と置き換える。
このとき、\(p\)と\(q\)は互いに素である。
これを(4)式…\(y^2 = 4JK\)に代入すると…
$$y^2 = 4p^2q^2$$
$$y = 2pq$$
となる。
なお、平方根を見る場合は本来マイナスも見るのだが、
最初の前提で\(y\)は自然数と置いているので、
プラスしか見ていない。
これで、\(y\)を表すことができた。
あとは\(x\)、\(z\)なのだが、
(2)式の\(J, K\)に\(p^2, q^2\)を代入して
軽く変形すれば得られる。
ちょっと離れているので、(2)式を再掲しておこう。
$$
\begin{equation}
\left \{
\begin{array}{l}
z + x = 2J \\
z – x = 2K
\end{array}
\tag{2}
\right.
\end{equation}
$$
まずは\(z\)から。
$$2z = 2(J + K) = 2(p^2 + q^2)$$
$$z = p^2 + q^2$$
次に\(x\)。
$$2x = 2(J – K) = 2(p^2 – q^2)$$
$$x = p^2 – q^2$$
やっと出た。
まとめると、以下の式が得られた。
$$
\begin{equation}
\left \{
\begin{array}{l}
x = p^2 – q^2 \\
y = 2pq \\
z = p^2 + q^2
\end{array}
\right.
\end{equation}
$$
これで証明完了だ。
かなり長かった、お疲れ様だ。
おわりに
さて、ここまで長々と証明を書いてきたが、
これを使って次回\(FLT(4n)\)を証明する。
実は今回が一番長く、
次回は今回ほど長くはならないはずだ。
というわけで、次回完結編、お楽しみに。
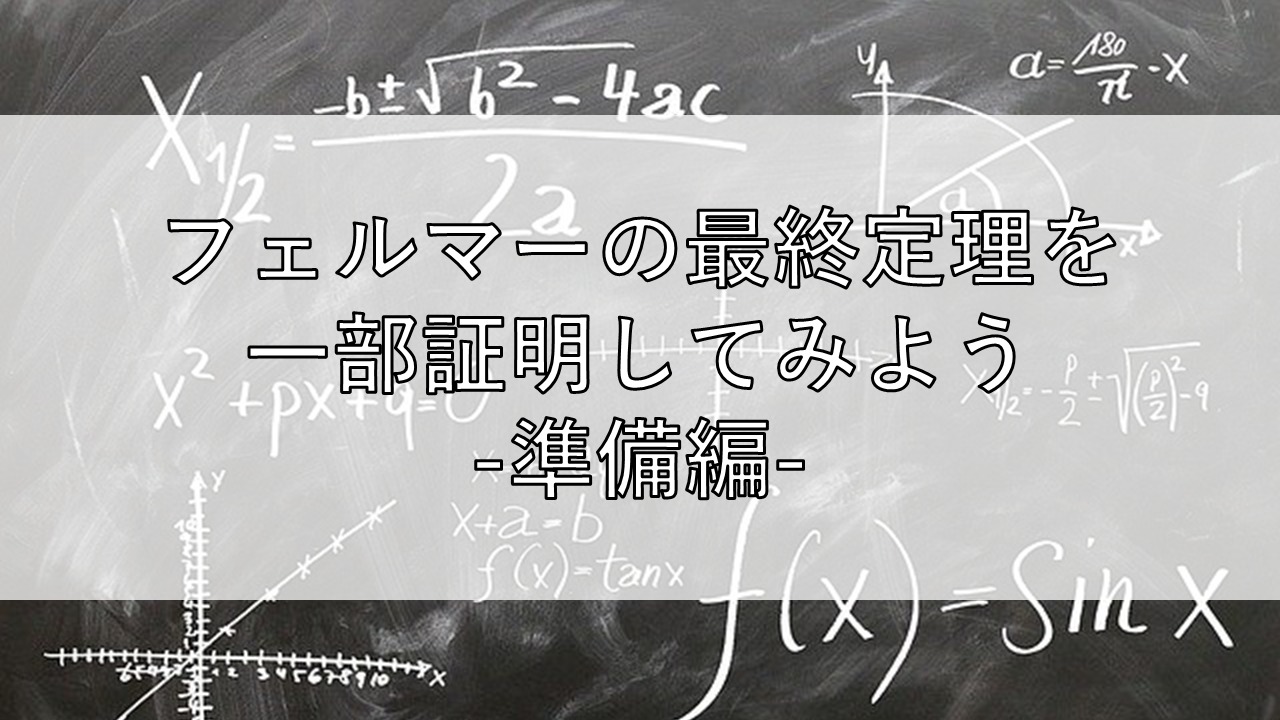


コメント